前回、英文読解の題材にするのは相対性理論でもくまのプーさんでも何でもよいという旨のことを書きましたが、今回はその「くまのプーさん(原題: Winnie-the-Pooh)」の一文を引用して英文の読み方を考えてみます。以前アインシュタインの相対性理論の一文を用いた時と同様、英文を英文として読む思考を2回に分けて私なりに考察してみます。
多読の教材について説明した時に童話は比較的短い文章で書かれていることが多いと述べましたが、今回はせっかくなので少し長めの一文を選んでみました。
下記の一文を読んでみてください。
One day, when Christopher Robin and Winnie-the-Pooh and Piglet were all talking together, Christopher Robin finished the mouthful he was eating and said carelessly: “I saw a Heffalump to-day, Piglet.”
英文を英語として読む
以前引用した相対性理論の一文ほどの「英単語の羅列感」はないと感じた人は少なくないかもしれません。しかし英文を読み慣れていないと途中で疲れてしまうこともあります。とは言え文体は平易ですので、いい機会なのでこれを英語の語順のまま英語として読んでみましょう。
頭の中ではこんなふうに考えながら読み進められます。
One day, when:One dayは「一日」ではなく「ある日」。whenが続くということは、この後「○○をした時」の○○の部分が文章で説明されるかも。
Christopher Robin and Winnie-the-Pooh and Piglet were:三人の登場人物だ。プーさんファンではなくてPigletを知らなくても、プーさんと一緒にいる誰か、くらいに考えて読み流してしまおう。
were all talking together,:(三人が)皆一緒に話していた(時)。「,」が付いているし、ここまでで意味が通る一文だから、whenの後に続く文章はここで終わるだろう。だとすれば次に本文が来る。
Christopher Robin finished the mouthful:本文の始まりっぽい。finishedは「終えた」。Mouthfulという単語を初めて見たとしても、mouth = 口、full = いっぱい(”l”が一つ足りませんが)だから、「口いっぱい」か「一口」くらいに考えておく。「Christopher Robinは一口食べ終えた」かな?
he was eating:「Christopher Robinは食べ終えた」と「彼は食べていた」をただ並べると、なんか変。慣れてくるとここに関係代名詞の「that / which」が省略されていることに気付きます。the mouthful that he was eatingで「(彼が)食べていた一口」。
and said carelessly::andが繋ぐものは何か?saidはsayの過去形だから、繋ぐものは多分動詞の過去形、「finished」だ。Finished and saidで「食べ終えて言った」。
“I saw a Heffalump to-day, Piglet.”:「””」で囲まれているから、いわゆる直接話法ですな。これくらい短い文章であれば「今日Heffalumpを見たよ、Piglet。」という意味を理解するまで、それほど時間がかからないのではないでしょうか。

文法は大事?
この一文には関係代名詞が省略されているというトリッキーな部分はありますが、使われている文法は難しくないということはお分かりいただけたでしょうか。「文法が分からないから英文が読めない」と言うのは言い訳でしょう。とは言っても、この一文をスッと読んでサッと意味が分かる、という人は多くないかもしれません。何故でしょう?
上記の省略された関係代名詞を無いものとして読むと「なんか変」で、「慣れてくる」と省略に気付くと書きましたが、私はこれが大事だと考えています。もちろん、文法の知識で十分に武装して全てを理論的に読解できて、そういう読み方が好きな人もいるでしょう。しかし、そのような読解方法が得意ではない人には「たくさん読んで、なんとなく慣れる」でもいいのではないでしょうか。
ここまで読んで「そうか、『習うより慣れろ』だ」と考えた人もいるでしょう。それも一つの考え方です。しかし、上記の一文を読んで、習ったことなのに理解できなかったと思った部分はありませんでしたか?そうであれば、「習ったことに慣れろ」も必要でしょう。英文読解のための始めの一歩は、新しい文法の知識を増やして頭でっかちになることではなく、今知っている文法に慣れることです。
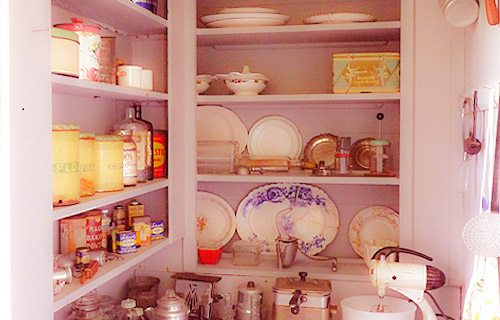
たかが文法。されど文法。文法は、それを知ってさえいれば英文読解ができるというものでは決してありませんが、かと言って不必要でもなく、飼い慣らせれば役に立ちます。
「継続は力なり」とは言いますが、
「たくさん読んで、なんとなく慣れる」とか、「習ったことに慣れる」とかいろいろ言いました。そのためには「英文を読む」ことを続けるということが大事だと理解することは難しくないかもしれませんが、難しいのはそれを実際に続けることですよね。
以前多読の実践についてお話した時に自分の興味がある分野の題材を選ぶことについて述べました。繰り返しになりますが、これは継続するために大事なことでしょう。私は相対性理論にも興味がある特異体質の持ち主の一人ですが、実は童話も好きで、Winnie-the-Poohも楽しく読んでいますし、これを読み終えたら「プーと大人になった僕(原題: Christopher Robin)」も見に行きたいと思っています。
随分前に、繰り返し使うことでなんとなく理解することを「人間的ディープラーニング」と例えて、そこで単語のカタマリをなんとなくパターンとして認識するという話をしました。「たくさん読んで、なんとなく慣れる」はこのことで、そのためには継続する力が必要です。みなさんも、これなら読める、という好きな英語の題材を見つけてはいかがでしょうか。
次回もWinnie-the-Poohから一文を引用しますが、今回より少しだけ複雑な文を選びます。





