Power in Language – 最近の報道によるとCalifornia州のBerkeley市では「gender preference」を含む表現を市の規約から除外する条例が可決されたそうです。この「gender preference」はどのようなもので、私たち英語学習者はここから何を学べるか考察してみます。前回の予告とは違う内容になりますが、その前に読んでいただきたい内容です。
これは日本のニュースでも一部で話題になっていましたが、せっかくですので英文のインターネット記事でどのように書かれているか見てみましょう。このCNNの記事は短いですので、英文Readingに慣れていない人も読破に挑戦してみてはいかがでしょうか。
Gendered language like ‘manhole’ will soon be banned from Berkeley’s city codes
Gendered Languageとは?
「Man」という単語は基本的に「(成人)男性」という意味ですが、状況によっては「人」という意味合いで使われることがあります。とは言え、Personという単語が性別に関係なく「人」を表すのに対してManという単語には「男性」という意味が含蓄されていますので、これを排除する動きがあるようです。上記の記事では「gendered language」や「gender preference」という表現が使われています。最近は日本でも「ジェンダー」という表現を耳にするようになりましたので、ピンと来るのではないでしょうか。
上記の記事ではgendered languageをgender-neutral termに置き換える以下のような具体例が挙げられています。
manhole → maintenance hole
manpower → human effort
どちらも日本で聞き慣れた言葉ですね。そもそもmanholeは「男性作業員が入る穴」に由来するという話を聞いたことがあります。これを性別的に中立な「保守作業用の穴」という言葉に置き換えるということですね。

他にも例としてpolicemenやpolicewomen、chairmenなどが挙げられています。前者は、日本でもかつては「婦警」という言葉が使われていましたので理解しやすいかもしれません (年配の方には)。しかし後者のchairmanを「議長」と和訳して理解してしまっては問題の本質が見えなくなってしまいます。私たち英語学習者はこれをどう捉えるべきでしょうか。
英語を英語として理解する
このブログでは度々「英語を英語として理解する」という話をしてきました。例えば以前「和訳ベースの理解からの脱却:メキシコは海外?」では、一部のカナダ人にとってメキシコは「abroad(外国)」ではあるが「overseas(海外)」ではないという話をしました。
この例では「overseas = 海外」と文字通りに変換することができますが、英語と日本語は根本的に異なる言語ですので英単語と日本語の単語が1対1で対応しているとは考えない方がいいでしょう。受験英語的に英単語を和訳して理解してしまうと英単語に含蓄される意味を見失ってしまうことがあります。
上記のCNNの記事で述べられている、市議会メンバーであるRigel Robinson氏の言葉を引用します。
“There’s power in language,” Robinson said. “This is a small move, but it matters.” [Cable News Network, 2019]
このpower in languageは英語を英語として理解してこそ分かることです。そこには和訳には表れないセンシティブな意味が含まれていることもあります。言葉に秘められた意味を理解することは異文化を理解することでもあると私は考えています。

コミュニケーションで大事な異文化理解
このブログではコミュニケーションとしての英会話を重視しています。ここでは言葉に秘められた意味と異文化理解について少し考えてみます。
言葉から異文化を理解する。
少しセンシティブな話をしましょう。日本でも少し前までは北米の先住民を「インディアン」と呼んでいました。この呼称は日本では「インド人」と訳されるIndianと同じ言葉です。これはアメリカ大陸に到着したコロンブスが、そこはインド亜大陸だと考え、そこにいた人達を「Indian」と呼んだことに由来しているそうです。しかし彼らはインド人ではありません。ひとつの単語をインディアンとインド人という別の単語に訳す日本ではこの問題の本質が分かりにくいかもしれません。
このことはつまり、英語を英語として理解すればコミュニケーションを深める一助になることも意味する。私はそう信じています。

ご存知の方も多いかもしれませんが、今ではアメリカ先住民をNative American、カナダの先住民をFirst Nationsと呼ぶのが一般的です。この「先住民」という言葉も英語ではIndigenous peopleと呼ぶ場合とAboriginal peopleと呼ぶ場合があります。このIndigenousとAboriginalの違いも興味のある人は調べてみてはいかがでしょうか、ぜひ英英辞典で。「先住民」という一つの訳語には表れない意味が見えてくるでしょう。
日本文化を理解する
言葉の問題から少し離れますが、異文化と日本の違いを理解することは、日本が異文化からどのように見られているかを理解することでもあります。つまり、日本文化を理解するということです。
今回は性別を意識した表現にまつわるインターネット記事から話を始めましたが、皮肉にも、時を同じくして話題になっていたのは日本の国会議員における女性の少なさについてでした。
Japan election: Surge of women candidates could reshape male-dominated parliament
この記事は少し長いですが、内容は日本でもよく報じられていたことですので、その背景知識を持って読めば少しは読み易いかもしれません。尚、このブログを書いている日の翌日は参議院選挙です。この記事のタイトルにある「could」はcanの過去形ではなく、「かもしれない」という意味で使われています。
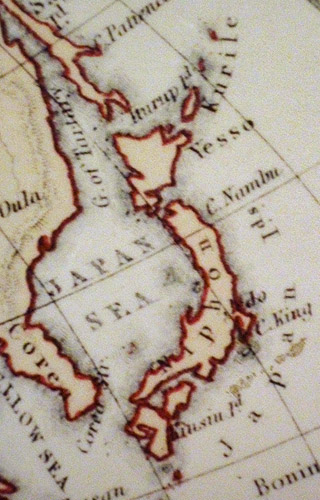
このように英語で書かれた日本の記事を読むと、日本が海外からどのように見られているのか少し分かるのでお勧めです。もちろん英文Readingの練習にもなります。
余談ですが、かつてアメリカでは…
選挙と男女問題といえば、前回のアメリカ大統領選挙ではHillary Clinton氏が当選した場合、夫のBill Clinton氏はどう呼ばれるかということが話題になっていました。大統領夫人がFirst Ladyだから、女性大統領の夫は、First Gentleman?これも和訳して考えたら分かりづらい話題ですね。結局Clinton氏は選挙に破れたため結論は出なかったと記憶していますが、実際はどうなのでしょう?
日本人を理解する
話を元に戻して、日本文化を理解することは英語のコミュニケーションにおいて大事だと私は考えています。前回予告したNaomi Osakaさんの話題は、実はこのことをメインテーマに考えていました。前回の予告からかなり時間が経ってしまいましたが、次はこの話をします。





